これまで自分が「宮沢賢治」「南方熊楠」「レヴィ=ストロース」「マタギ」「東北」等々に惹かれてきた理由、ここにありました。あぁ、とてもすっきり。
このシリーズ、とてもためにもなって面白いです。
「対称性」視点で世の中を見ることをこれからもっと意識的に行っていこう。
米同時多発テロと神話学――。この2つが根本のところでかかわっていると聞けば、異様な感じを受ける向きも多いだろう。だが、テロであれその報復であれ、すべての「野蛮」は神話的価値観の終焉がもたらしたといえるのだ。
本書は「超越的なもの」について、太古から人類が巡らせてきた思索を追うシリーズの第2巻。原初の共同体が崩壊し、王と国が生まれるまでを考察する。著者はアムール川流域やサハリン、北米、南米などに伝わる数多くの神話を分析、自然と人間が互いに尊重し、交流していた社会の姿を探り出してゆく。ここでは、人と動物が単なる狩り狩られる関係ではなく、人間も毛皮をまとえば獣となり、雌とつがって子を産ませるというような伝承が生じる。また、無差別に動物を殺戮することなどありえず、生きるために殺しはしても、骨や毛皮は敬意をもって扱われた。人と自然が相互に往き来できる世界、いわば「対称性の社会」なのだ。こうした世界では、「権力」は本来、自然が持つものであり、社会の外にあった。人間のリーダーである「首長」は、交渉や調停といった「文化」の原理で集団を導く者だったのだ。だが、この「権力」が共同体内部に持ち込まれたとき、人間と自然は隔絶し、首長は王となって、国が生まれた。「権力」を取り込むことで成立した「国」は、人や自然を一方的に支配しようとする宿命を持つ。ゆえに国家というものは本質的に野蛮をはらんでいるのだ、と著者は言う。
本書のもとになった講義は、同時多発テロの直後に開始された。その影響は色濃く、本文のなかでも、文化とは何か、野蛮とは何かという問いかけがしばしばなされている。著者は国家という野蛮に抗しうる思想として、仏教の可能性を考察する。ブッダの生家は共同体に近いような小邑の首長であり、この出自が仏教の性格に影響を及ぼしているという。とすれば、原初の精神が21世紀の混迷を照らすということになるだろう。きわめてダイナミックな構図だが、こうした示唆こそ神話を学ぶ意味なのかもしれない。(大滝浩太郎)
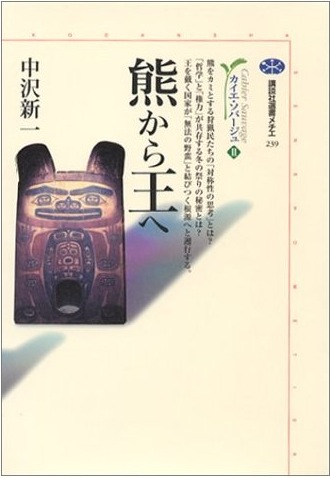
コメントを残す